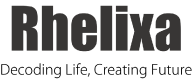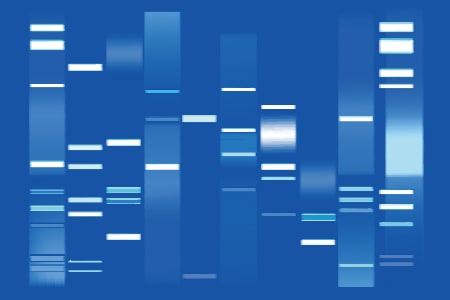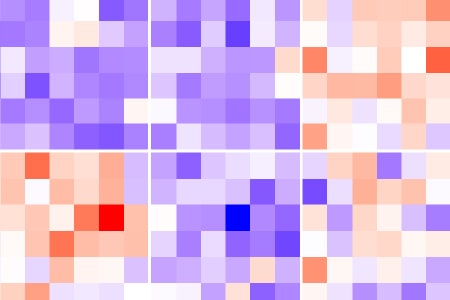この節から学ぶこと
- ・エピゲノムの具体的な解析方法を知る
- ・ヒストンのエピゲノムの解析方法に「ChIP-seq」や「ChIP-qPCR」がある
- ・メチル化DNAの解析方法に「バイサルファイト処理」がある
エピゲノムを調べる
ここまでエピゲノムの仕組みや応用例について解説しました。
「クロマチン構造の変化とRNA合成」で述べたように、エピゲノムのメカニズムのうち重要なのは以下の2つです。
- ・ヒストンの修飾
- ・DNA自身の修飾
エピゲノムを調べる効果について、例を考えてみましょう。
ある薬剤与えた細胞と与えなかった細胞を用意してその両方のエピゲノムを調べて比較すれば、その薬剤がどの遺伝子の発現にどう作用するのか、エピゲノムの観点から理解できるようになります。
そのためには、どのヒストンのどこが修飾されているのか、DNAのどの部分がオープンクロマチンになっているのか、DNAのどの部分が修飾されているのかを調べることになります。
この章では、エピゲノムを調べる手法について簡単に紹介します。
エピゲノムの解析の流れ
エピゲノムの解析は標準的には下記のような流れになります。
- 1. 細胞からDNAを取り出す
- 2. DNAに化学的な前処理を行う
- 3. DNAの塩基配列をシーケンサーで読み取る
- 4. 1次解析を行う
- 5. 2次解析を行う

ヒストンのエピゲノムの解析法
最初に紹介するのは、ヒストンの修飾(アセチル化やメチル化など)を調べる手法です。
ヒストンの修飾は遺伝子発現と関係します。例えば、ヒストンがアセチル化されたところはオープン・クロマチンになりやすく、RNAに転写されやすい、つまりDNAのその位置の遺伝子が発現しやすい状態にあります。
そこで、アセチル化されたヒストンだけと結合する物質(抗体)を用意します。この抗体を使えば、アセチル化されたヒストンを見つけることができます。このヒストンがDNAのどの位置にあるかを調べれば、発現しやすい状態になっている遺伝子がわかります。
上記のようにしてヒストンのエピゲノムを調べる方法は「クロマチン免疫沈降法」といいます。
この方法には、
- ・「ChIP-seq(チップ・セック)」:すべてのゲノムのヒストンの変化を網羅的に調べる方法
- ・「ChIP-qPCR」:特定の遺伝子に限定して調べる方法
などがあります。
また、 クロマチン免疫沈降法ではない方法として、
- ・「ATAC-seq(アタック・セック)」:RNAに転写されやすいオープン・クロマチンの領域のみの塩基配列を解析することによって、オープン・クロマチンがDNAのどの位置にあるかを調べ、それによって発現しやすい状態になっている遺伝子を知る方法
があります。
DNAのエピゲノムの解析法
DNA自身のメチル化を調べる方法はいくつかあります。
しばしば用いられる方法は「バイサルファイト(BS)処理」というものです。
この処理を行うと、
メチル化されたシトシンはそのまま、
メチル化されていないシトシンは「ウラシル」という別の塩基に変化します。
これを利用して、ウラシルに変化したかどうかで、その場所のシトシンがメチル化されたかどうかを調べるのです。
実際には、
- ・「メチル化特異的PCR法(MSP法)」:特定のシトシンの場所のみ調べることができる方法
- ・「 BS-seq」:もう少し広い範囲でシトシンのメチル化を調べることができる方法
などの様々な手法があります。
さらに、ゲノム全体を網羅的に調べる方法として
- ・BeadChip
- ・全ゲノムバイサルファイトシークエンス法(WGBS)
があります。こちらもChIPと同様、調べる範囲や精度に合わせて手法を使い分ける必要があります。
エピゲノム研究ならレリクサにお問い合わせください
M.D.を含む15名以上のPh.D.研究員が在籍。専門の研究チームが研究プロジェクトの目的や予算、期間に応じて最適なプランをご提案し、あなたの研究開発を最適化するベストプラクティスを提供します。
お問い合わせはこちらから
丁寧なビフォアサポート・アフターサポート
高い専門性と丁寧なサービスで、最後までご満足いただけるサービスを提供します。
リーズナブルで高品質なシーケンス
競争力のある国内外シーケンスプロバイダーと提携し、低価格・高品質なデータ取得を実現しています。データ解析をご自身で実施するお客様からも選ばれています。
カスタム実験・オーダーメイド解析・統合解析にも対応
ご研究目的やご要望の図版、参考文献等に応じて、標準サービスメニュー外のカスタム実験・カスタム解析・マルチオミクス解析・統合解析も承ります。
株式会社Rhelixa(レリクサ)について
当社は最先端のゲノム・エピゲノム解析で培ってきた技術を活用して、生物学・医学・薬学領域における基礎研究や製品・ソリューションの開発、またはそれらの受託業務を行っています。次世代シーケンサーにより得られるエピゲノムデータの他、ゲノムやトランスクリプトーム、メタゲノムデータを組み合わせた統合的なデータ解析により、細胞制御の詳細なメカニズムの予測や精度の高いマーカーの探索を行います。また、研究開発のあらゆる場面で必要となるデータの統計解析や図版作成を基礎知識を必要とせず誰もが手元で実現できる環境を提供しています。